示談交渉による交通事故解決② 〜示談交渉の注意点〜
目 次 [close]
示談交渉の注意点
示談交渉の時期
示談交渉は、法律上の損害賠償請求権の内容について合意することを目的としていますので、被害者側に生じた損害が確定し、客観的に金銭的評価ができる状態とならなければ、示談を行うことは通常ありません。
傷害事故の場合
傷害事故の場合には、被害者の傷害という損害の全体が明らかになる時、つまり治癒又は症状が固定した段階で示談交渉を始めることが一般的です。症状の固定とは、医学上一般に承認された治療方法をこれ以上継続しても症状の改善が期待できない状態で、かつ残存症状が自然的経過によって到達する最終の状態、つまりこれ以上回復することはない状態をいいます。
傷害の場合にはどうしても治療によって完全な回復ができないことがあるので、そのような場合にはいつまでたっても傷害の損害の内容が確定せず、示談交渉ができないこととなります。そこで、傷害に関して発生した損害については、症状の固定という段階で確定させ、それ以後に残った症状については、後遺障害という将来にわたって継続する別個の損害として症状固定時において金銭的に評価し確定させることで、問題の早期解決を図ることとされているのです。
もっとも、傷害事故では被害者が当面の治療費を支払うために、損害が確定する前に内払(仮払)を請求することも行われます。加害者から、一括支払を主張され内払を断られることもありますが、最終的な示談交渉を円滑に進めるために内払の請求に応じることもあります。
※ 後遺障害等級とは、回復の見込みのない後遺症が残った場合に、その後遺症によって生じた損害(収入減少や精神的苦痛)の金銭的評価の指標とするため、後遺症の態様を分類・序列化したものです。後遺症についての損害賠償額は、後遺障害等級の認定に基づいて定められることが一般的です。自賠責保険では後遺症の内容を等級(1~14級)に分類した後遺障害認定の基準が法令によって規定されています。事故によって生じた症状が回復の見込みがなくなった状態(症状固定といいます。)でなければ後遺障害等級は認定されませんので、後遺症についての損害賠償額の確定には症状の固定を要します。
示談交渉においては、症状の固定があるかどうかが争われるケースが多くなっています。医学的見地からの判断の難しさに加え、保険会社が被害者の治療費を内払いしている場合などは、保険会社としては治療を停止することを期待しますし、被害者としては治癒を期待して治療を継続することを希望するという利害対立が生じるからです。
なお、医療機関が診療の初期において「全治6ヶ月」などの診断書を出すことがありますが、症状固定の有無は、あくまでも被害者の現在の状態について、一般的な医学的知見に基づいて作成された最新の診断書において判断されることとなります。
死亡事故の場合
死亡事故の場合は、被害者が亡くなった時点で損害が確定します。そのため、被害者の相続人は、事故後いつでも示談交渉を開始することができます。
示談交渉と消滅時効
不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年が経過すると消滅するとされています。
なお、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の時効は、5年となります(民法724条の2)。そのため、交通事故の人身損害については、原則、損害及び加害者を知った時から5年が経過すると消滅するとされています。
示談交渉においても、事故から5年以上経過していると、加害者は時効消滅を主張して、損害賠償に応じないことがほとんどです。
示談交渉を進捗させる際は、損害賠償請求権が時効の完成により消滅していないかについて、注意しなければなりません。
示談交渉の当事者
請求の相手方としての法律上の賠償責任者
被害者としては、事故を起こした加害者に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができるのですから、1次的には加害者が示談交渉の相手となります。
また、加害者以外の者であっても、運行供用者責任を負う者、使用者責任を負う者、監督者責任を負う者も、示談交渉の相手方となります(詳しくは民法上の不法行為責任及び運行供用者責任のページをご覧ください。)。
このように、1つの事故について直接の加害者以外にも複数の損害賠償義務を負う者がある場合には、その全員に対して被害者が請求することもできますし、そのうちの1人に対して請求することもできます。もっとも、最終的に被害者が受け取ることのできる賠償金の額は法律上同じですので、被害者側としては誰が損害賠償義務を負うかという法律的判断を前提にして、損害賠償が可能な資産や支払能力のある者との交渉を先行させ、賠償金が現実に受け取ることができるようにすることを検討します。
保険会社の示談代行がなされている場合
自動車を保有している人は、自身が加害者として損害賠償金を支払うこととなった場合に備えて、その損害賠償金を保障する自動車保険に加入していることが通常です。加害者が示談代行付きの任意保険に加入していれば、現実に被害者が交渉する相手は、加害者の任意保険会社の示談代行担当者となることが一般的です。
示談代行者は被害者よりも専門的知識を有しており交渉力も優ることが多いので、被害者としては自己に不利な交渉とならないように注意する必要があります。しかし、一方で事故の当事者でない人との交渉では感情的にならずに客観的に交渉を進めることができますし、加害者本人が多忙であれば交渉が円滑に進まないこともありますので、利点もあります。実際の示談交渉では、ほとんどが保険会社の示談代行担当者と示談成立に至っているという現状からすれば、よほど保険会社が不誠実な対応をしない限りは、示談交渉が円滑に進むといえます。
なお、保険会社との交渉の際には、求められる資料等は原則として提出した方が、交渉が円滑に進みます。
また、治療費の内払いを求める場合などは、被害者の受診している医療機関の診断書や検査画像を保険会社が取り寄せることに同意する書面の提出を保険会社から求められることが一般的です。
被害者が死亡している場合
被害者が亡くなってしまった場合、被害者の法律上の損害賠償請求権は被害者が有していた財産として、その相続人が相続するとされています(民法896条参照)。相続人でなくとも一定の範囲の遺族は、自己の精神的苦痛について損害賠償請求をすることができます(民法711条)。例えば、被害者(夫)の配偶者と子どもが残された場合は、その配偶者と子どもが相続人となりますので(民法887条1項、890条参照)、被害者の逸失利益について損害賠償請求ができます。また、相続権のない被害者の両親は子どもを亡くした精神的苦痛について慰謝料を請求することができます(民法711条)。
交渉相手である加害者側としては、だれが相続人であって相続の割合がどのようであるか、遺言はなかったかという事情を知ることができません。そうすると加害者側としては相続人の1人と示談を成立させても、後から別の相続人と称する人から相続の割合が違うとか、損害賠償額が違うなどと主張されてしまう可能性があるので、複数の相続人と個別に交渉に応じることは困難です。
したがって、被害者側としては、こうした相続についての問題を示談交渉の障壁としないためにも、相続人全員の合意で交渉担当者を決め、交渉を一本化することが必要となります。
物損事故の示談交渉
人の死傷が生じなかった交通事故では、自賠責保険は利用できません。加害者が対物賠償保険に加入していなければ自動車保険による救済は受けることができないことになります。
したがって示談交渉にあたってはまず事故証明書などによって自己の相手方がどのような保険に加入しているかを確認することが重要となります。
相手方が対物賠償保険に加入している場合には、保険会社が示談代行をすることがほとんどですが、そうでなければ直接に相手方との交渉となります。
なお、人が受傷していないとしても、義眼、義歯、義肢、眼鏡、コルセット、松葉杖、補聴器などは、身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行していることから、「身体」(自動車損害賠償保障法3条)として自動車損害賠償保障法が適用され、自賠責保険が利用できるので人身事故と同様の扱いとなります。
過失割合についての示談交渉
過失割合には認定基準がありますが、具体的な事故においては基準に該当しない事情もあり、示談交渉においては過失割合が争点になることが少なくありません。
過失割合の認定基準については保険会社も裁判所と同様の基準に基づいて過失相殺を主張することが多いので、こうした過失割合についての争いは事故の態様や詳細な状況がどうであったかという事実関係の問題が中心となります。
そこで、事故から時間が経過した後に行われる示談交渉では、事故状況に関する資料を確保し、正確に事故状況を把握するとともに相手方を説得するための証拠とする必要があります。資料について、例えば、事故当時に事故を警察に届けていると自動車安全運転センターから交通事故証明書という書類が発行されますし、被害者は、警察が作成した事故の実況見分調書や現場見取り図といった刑事記録の閲覧・謄写を検察庁や裁判所に請求することができます(犯罪被害者保護法3条1項、刑事訴訟法53条1項など)。
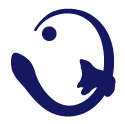
小西法律事務所


 前の記事へ
前の記事へ