交通事故による損害額の算定③ 〜後遺障害による逸失利益〜
交通事故における損害賠償は主に積極損害、消極損害、慰謝料の3つに分けることができます。
そのうち消極損害とは、事故にあわなければ将来得られたであろうと考えられる利益を失ったことによる損害をいいます。消極損害は、更に休業損害と逸失利益の2つで構成されます。
目 次 [close]
逸失利益とは
逸失利益とは、事故がなければ被害者が将来得られるであろう経済的利益を失ったことによる損害です。
逸失利益には、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益があります。
後遺障害による逸失利益
後遺障害逸失利益は、以下の算定式により計算します。
後遺障害逸失利益=基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入
逸失利益算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とします。もっとも、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。なお、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定することができます。
*賃金センサス
賃金センサス(census=官庁の行う大規模統計調査) とは、厚生労働大臣官房統計情報部の企画の下に、都道府県労働局および労働基準監督署の職員および統計調査員によって行われている賃金に関する統計を意味します
有職者
給与所得者
原則として事故前の収入を基礎として算出します。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサスによる算出を認めます。
ただし、若年者(概ね30歳未満の者)については、実収入額が学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と学歴計・全年齢平均賃金との元離の程度、その原因等を総合的に考慮します。また、将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は、学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。その蓋然性が認められない場合であっても、直ちに実収入額を基礎とするのではなく、学歴別・全年齢平均賃金、学歴計・年齢対応平均賃金等を採用することもあります。なお、大卒者については、大学卒・全年齢平均賃金との比較を行います。
- 事故前の収入
収入には、本給のほか、歩合給、各種手当(残業手当・扶養手当・家族手当)、賞与を含みます。ただし、通勤手当については、事故により算出を免れる性質として否定した裁判例があります(大阪地判平成3年1月17日)。 - 将来の昇給
公務員など給与規定、昇給基準が存在する場合に考慮される例が多いようです。また、最判昭和43年8月27日は、将来の昇給が証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には、昇給回数、金額等を予測し得る範囲で控えめに見積もって、これを基準として算出することも許されると判断しました。 - 定年制
公務員など給与規定、昇給基準が存在する場合に考慮される例が多いようです。また、最判昭和43年8月27日は、将来の昇給が証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には、昇給回数、金額等を予測し得る範囲で控えめに見積もって、これを基準として算出することも許されると判断しました。 - 退職金
後遺症により退職してしまった場合、定年まで勤務した場合の退職金額から現実に支給された退職金との差額を逸失利益として認める場合があります。
事業所得者
自営業者、自由業者、農林水産業などについては、申告所得を参考にしますが、同申告額と実収入額が異なる場合には、立証があれば実収入額を基礎として逸失利益を算定します。
所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定します。
会社役員
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は算定の基礎として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は算定の基礎とされない傾向にあります。
家事従事者
専業主婦
専業主婦については、原則として、基礎収入を全年齢平均賃金によりますが、年齢・家族構成・身体状況・家事労働の内容などに照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、年齢別平均賃金を参照して適宜減額をするとされています。
有職主婦
有職主婦の場合については、実収入額が全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額によりますが、下回っているときは、専業主婦の場合と同様に処理するとされています。有職主婦の場合、通常家事労働分の加算は認められていません。
最判昭和49年7月19日では、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。」され、専業主婦につき「平均的労働不能年令に達するまで、女子雇用労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である。」との判断がなされています。
無職者
幼児・生徒・学生
原則として、学歴計・全年齢平均賃金を基礎としますが、大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については、大学卒・全年齢平均賃金を基礎として逸失利益を算定します。
年少女子については、原則として、男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を用いることとされています。
未就労者の逸失利益の算定方法については,次のとおりです。
幼児・生徒・学生以外のその他の者
就職の蓋然性がある場合には、損害が認められます。その場合、基礎収入は、年齢別平均賃金によります。
失業者
失業者については、再就職の蓋然性のある場合に逸失利益の算定が可能となり、基礎収入は、再就職によって得ることができると認められる収入額によるとされています。その認定に当たっては、以下の諸点に留意し、失業前の実収入額や全年齢平均賃金または被害者の年齢に対応する年齢別平均賃金などを参考にします。
すなわち、おおむね30歳未満の者の場合については、再就職によって得られる予定の収入額または失業前の実収入額が、年齢別平均賃金より相当に低額であっても、現在の職業、事故前の職歴と稼働状況、実収入額と年齢別平均賃金または学歴別かつ年齢別平均賃金との乖離の程度およびその乖離の原因などを総合的に考慮して、将来的に生涯を通じて全年齢平均賃金または学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金により算定することになります。ただし、前記の予定収入額または実収入額と年齢別平均賃金との乖離の程度が大きく、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められないような場合には、年齢別平均賃金または学歴別平均賃金の採用なども考慮します。
このように、失業者は、労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性がある者については、事故前の収入や賃金センサスを参考にし、被害者の具体的な事情によって判断されます。
休業損害とは異なり、事故時点で収入がないからといって、将来にわたって収入が得られないとするのは不合理で、あるため、原則的に逸失利益は肯定される傾向にあります。
外国人
永住資格等の在留資格を持っている外国人の場合
日本人と同様の方法で逸失利益を算定します。
不法就労している外国人の場合
予想される就労期間あるいは滞在期間内は日本における収入を基礎とし、その後は本国の収入額を基礎として逸失利益を算定します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度をいいます。
労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価します。
労働能力喪失期間
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度をいいます。
労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価します。
労働能力喪失期間の始期は症状固定日です。
未就労者の就労の始期については原則18歳とされますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時となります。
労働能力喪失期間の終期は,原則として67歳です。
症状固定時の年齢が67歳をこえる者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とします。
ただし、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされる場合があります。
事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもあります。
例えば、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断する必要があります。
中間利息控除
労働能力喪失期間の中間利息の控除は、大阪地裁はライプニッツ式(ライプニッツ係数)によられています。
中間利息控除の基準時は症状固定時とするのが実務の大勢ですが、事故時とする裁判例も見られます。
*ライプニッツ係数とは
逸失利益の請求は、長期間にわたって発生する収入減少による損害を、一時金で受け取ったため、将来の利息分(中間利息)を差し引き計算することにより、将来の利益を現在の価値に換算する必要があります。すなわち、もらったお金を運用すれば、利息がついて増えるのですから、現在請求できる額は、将来もらえるはずの金額から、それまでの利息分を控除した金額ということになります。
中間利息控除率は年5%のライプニッツ係数を用いるのが通常です。
生活費控除の可否
後遺症逸失利益の場合は死亡逸失利益の場合と異なり、生活費を控除しないのが原則となります。
有職者または就労可能者
労働能力喪失期間の始期は症状固定日です。
具体例
症状固定時の年齢が55歳で年収500万円の男性サラリーマンが傷害を負い後遺症により労働能力が35%低下した場合。
500万円 × 0.35 × 8.8632(*1)=1551万0600円(*2)
(*1):55歳から67歳までの就労可能期間12年のライプニッツ係数
(*2):稼働年数12年、生活費は控除しません。
18歳(症状固定時)未満の未就労者
(*1):18歳未満の者は、就労の始期が18歳となるから、18歳に達するまでの係数を差し引く必要があります。
具体例
10歳の男子が傷害を負い後遺症により労働能力が35%低下した場合
560万9700円(*2) × 0.35 × 12.2973(*3)=2414万4457円
(*2):令和元年男性労働者学歴言十全年齢平均賃金
(*3):10歳に適用するライプニッツ係数は次のように求める。
67年−10年=57年に対応するライプニッツ係数18.7605
18年−10年=8年に対応するライプニッツ係数6.4632
18.7605―6.4632=12.2973
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度をいいます。
労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体例にあてはめて評価します。
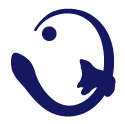
小西法律事務所


 前の記事へ
前の記事へ