個人情報保護法~認定個人情報保護団体の制度について
個人情報保護委員会は、個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした民間団体による自主的な取り組みを支援するため、認定個人情報保護団体の制度を設けています。
本コラムでは、認定個人情報保護団体の制度について解説いたします。
認定個人情報保護団体の業務内容
認定団体の業務は、以下のとおりです。(法47条1項)
- 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理
- 対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項について対象事業者への情報提供
- その他、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関する必要な業務
上記の中でも主な業務は苦情の処理となります。認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、必要な助言や事情の調査をし、対象となっている事業者に苦情の内容を通知します(法53条1項)。必要があると認めるときは、事業者に対して説明や資料の提出を求めることができます(法53条2項)。認定個人情報保護団体からこの求めがあったとき、事業者は正当な理由なく拒むことはできません(法53条3項)。
また、認定個人情報保護団体は、各業界特有の事情に配慮しつつ、個人情報保護法の趣旨に沿ったガイドラインを作成するよう努めなければなりません(法54条)。
欠格事項
以下のいずれかに該当する者は、認定個人情報保護団体として認定を受けることができません。(法48条)
- 個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法155条1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務を行う役員のうち、次のいずれかに該当する者があるもの
・拘禁刑以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・法155条1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
認定の基準
認定個人情報保護団体の認定を受けるには、以下の基準をすべて満たしていなければなりません。
- 法47条1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施方法が定められていること。(法49条1号)
- 法47条1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すること。(法49条2号)
- 法47条1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないこと。(法49条3号)
認定の変更
認定個人情報保護団体が、その認定業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければなりません。ただし、法47条1項各号に定める業務の内容の実質的な変更を伴わない軽微な変更であればこの限りではありません(法50条)。
廃止の届出
認定個人情報保護団体が、認定業務を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならず、届出を受けた個人情報保護委員会は、その旨を公示しなければなりません(法51条)。
対象事業者
認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならず、対象事業者とした場合は氏名又は名称を公表しなければなりません。また、認定個人情報保護団体は、個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとったにもかかわらず、対象事業者が法54条1項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができます(法52条1項、2項)。
認定団体の信頼性の確保
認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報の目的外利用を禁止されており(法55条)、名称についても使用制限を受けています(法56条)。
また、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に対して以下の権限を有します。
- 認定業務に関し報告をさせること(法153条)
- 認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずること(法154条)
- 認定を取り消すこと(法155条)
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
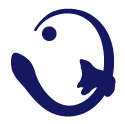
小西法律事務所


 前の記事へ
前の記事へ